夕焼け茶房新装開店 |
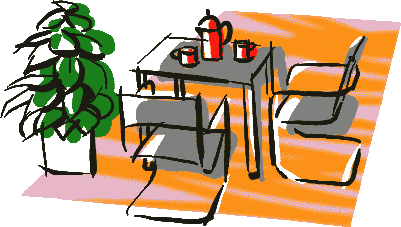 2005年〜2008年まで、東京新聞にコラム「遊ぶ・学ぶ」を連載していました。 2005年〜2008年まで、東京新聞にコラム「遊ぶ・学ぶ」を連載していました。英語学習・英語劇・教育論・湯西川・その他について、書き綴ってきた記事です。 「読んでみたかった。」という皆様のリクエストにお応えして?それらの文章をここに少しずつまとめさせていただきます。 お茶でも飲みながら読んでみてくださいませ。 2009.4.29 店主 FUKUDA |
夕焼け茶房新装開店 |
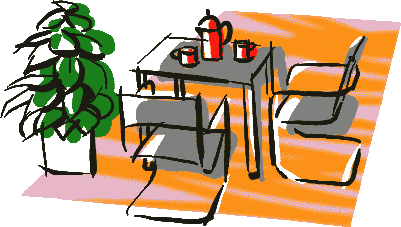 2005年〜2008年まで、東京新聞にコラム「遊ぶ・学ぶ」を連載していました。 2005年〜2008年まで、東京新聞にコラム「遊ぶ・学ぶ」を連載していました。英語学習・英語劇・教育論・湯西川・その他について、書き綴ってきた記事です。 「読んでみたかった。」という皆様のリクエストにお応えして?それらの文章をここに少しずつまとめさせていただきます。 お茶でも飲みながら読んでみてくださいませ。 2009.4.29 店主 FUKUDA |
| お品書き | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平成18年度の遊ぶ・学ぶ | 内 容 | 新聞掲載日 | ||
| 1 | 英語で学べ!子どもたち | 小学校英語に悩める先生方へ | 2005.5.20 | |
| 2 | クリケットはいかが? | ALTと子どもたちのふれあい | 2005.7.15 | |
| 3 | 児童劇の天使たち | 世界へ羽ばたいた天使たち | 2005.8.19 | |
| 4 | 米国と日本の児童劇 | 私のちょっとした児童劇論 | 2005.9.30 | |
| 5 | 牛乳でカンパイ! | 劇の成功を祝って乾杯! | 2005.11.18 | |
| 6 | 1年生、英語劇に挑戦! | 英語劇「ふぅあぁゆぅ?」 | 2006.1.20 | |
| 7 | 卒業生たちよ、幸多かれ! | 足利市立梁田小学校の卒業式 | 2006.3.17 | |
| 平成19年度の遊ぶ・学ぶ | ||||
| 8 | 教育の原点はへき地にあり | 縁あって湯西川へ異動しました。 | 2006.4.21 | |
| 9 | 地域ではぐくむ子どもたち | 平家大祭のお話 | 2006.6.15 | |
| 10 | 待ちわびていた「再開交流」 | 再開した湯西川と板橋区の小学生 | 2006.7.21 | |
| 11 | 真昼の引っ越し大作戦 | 学校のお引っ越し! | 2006.9.1 | |
| 12 | 湯西川 教員寮物語 | 今はなき大新寮の思い出 | 2006.9.29 | |
| 13 | 鎌倉の大仏様への手紙 | 合同修学旅行 | 2006.10.19 | |
*4年分ありますので順次公開します! |
 |
|||
| 英語で学べ!子どもたち 小学校英語に悩める先生方へ記念すべき東京新聞 連載第1回 2005.5.20 |
| 小学校英会話学習担当者会議では、毎回、様々な現場の意見が飛び交っている。 「なかなか児童に英語が定着しない。覚えてもすぐに忘れてしまうが、どうしたらいいか。」 という質問があった。同じ悩みをもっていた先生方は少なからずいたようである。会議を主催する指導主事は、定着まで考えなくてもよいのではないか?と個人の考えをしめしていた。 私は、この考えに賛成だった。小学生にとって、英語の定着を図った授業は必要ないと考えていたからである。 確かに、英語の語彙を積み上げていかなければならないという考えも分かる。しかし、言葉の勉強の第一歩として、もっと大切なものは他にあるはずだ。それは、英語という言葉を「体で受け止めさせること」さらに、何を伝えようとしているのかを察する「カンを育てること」である。 英語を使って遊ぶことは、ここに意味がある。 私の勤務する小学校では、昨年度一年間、、二人のEAA(英語活動協力員)を迎え、担任の先生方とのティームティーチングに取り組んだ。 英語のジャンケンの授業もあった。 「ロック・ペイパー・シザース・1・2・3!アイウォ〜ン!」 子供たちは覚えたばかりの英語で蛇おにや王様ジャンケンを楽しんでいた。昼休みの校庭にも、子供たちの大きな声が響き渡っていた。他にもEAAの二人からは、出身国の遊び「パテンテロ」など、いろいろな遊びやゲームを教えていただいた。 授業後、「英語の勉強は、みんなで遊べるから楽しい。」という感想が大半を占めていた。 また、「たぶんEAAの先生は、こう言っているのだろう?と想像していたら、その通りだった!」 と話す女の子もいた。 現在、多くの大手英会話スクールでは、簡単な会話を英語の遊びを通して子供たちに教えている。もちろん、これだけで英語がいきなりペラペラになることはない。だが、相手が伝えようとしている話の内容を(たとえそれが英語であっても)自分なりに受け止めて、積極的に理解しようとする姿勢を養うことができる。 小学生の場合、言葉の定着そのものを目標とする授業より、遊びを通して英語環境を体感させる授業の方が、得るものは大きい。 「週に一時間では定着は難しい。朝学習で復習したり、英語の歌をたくさん歌わせているがそれでも今ひとつ。もっと効果的な方法はないか?」と心配する必要はない。 まずは、たっぷり英語で遊ばせてみよう。 英会話だけでなく、人との関わり方もきっと学んでくれるはず。 |
| クリケットはいかが? オーストラリアから来たALTのお話 2005.7.15 |
| 雨上がりの校庭で、何やら珍しいスポーツに興じている子供たちと外国人教師がいます。 楕円形のグラウンドの両端にはバッターが向かい合っています。 ピッチャーと思われる子も二人います。あっ!バッターがボールを打ちました。あれ?バットを持ったまま走っています。バッターの後ろにある、三本の棒の上にのった不思議な物体が地面に落ちると大きな歓声が上がりました。 野球のようで野球ではないこのスポーツは「クリケット」といいます。日本人には、あまりなじみのないスポーツですが、発祥の地であるイギリスを筆頭に、ヨーロッパやアフリカ諸国、オーストラリア・インド・スリランカなど、現在では全世界の競技人口がサッカーについで二番目に多いそうです。 今年の四月から本校に英会話指導員として勤務しているクリス先生は、オーストラリア人。当然、小さな頃からクリケットに親しんできました。先日、英会話の授業で、「スポーツの名前」を勉強しましたが、子供たちから「クリケット」の名前はついに出てきませんでした。 クリス先生は、その時、少しばかり寂しく感じたにちがいありません。 「クリケットを子供たちに教えたいのですが、どうでしょうか。」 ある日、英会話学習の担当である私に、クリス先生が相談を持ちかけてきました。 「クリケットって、むずかしくないの。」 「だいじょうぶ。オーストラリアでは小さな子供もやってます。」 彼は目を輝かせて真剣にクリケットのすばらしさを語り出しました。 インターネットで調べてみると日本でもどんどん普及しているようです。子供でも十分楽しめそうです。小学生用のクリケットセットもネットで入手可能でした。フェアプレイ精神に富んだスポーツであることなど、教育的価値も十分にあります。 数日後、校長先生の許可を得て購入した子供用のクリケットセットが届きました。 その日から、校庭ではクリケットを楽しむ子供たちとクリス先生の姿が見られるようになりました。クリケットを国際理解の授業に取り入れた学年もあります。 クリス先生は、子供たちの前では休み時間であっても日本語を使いません。もちろんクリケットについてもすべて、英語とジェスチャーで説明しました。 子供たちは、すんなりとルールを飲み込んだようでした。 バッターは、バッツマン。ピッチャーは、ボウラー。そして、三本の棒の上にあったのはウィケットと言うそうです。私は子供たちから教わりました。 |
| 児童劇の天使たち 世界へ羽ばたいた天使たち 2005.8.19 |
| 数年前に、「真夜中のサンタクロース〜天使が舞い降りた夜に〜」という児童劇の脚本を書き上げました。 そこに登場させた5人の天使たちは、インターネットの風に乗り、日本全国の学校に飛び立ちました。 そして、訪れた各地の子供たちに、劇の楽しさを伝えてきたのです。 やがて、天使たちは、アメリカやカナダの学校を訪問し、地球の向こう側からも好評を得るようになりました。 国内外を問わず、子供たちは「劇」が大好きです。演じることも作ることも大好きです。劇の持つ教育的効果は、多くの先生方や研究者が認めている「事実」ですが、子供たちが劇に取り組める機会は、年々少なくなっているように感じます。 確かに、学校五日制の現在、授業時数を何が何でも確保しなければならないという「忙しい時代」であることは理解できます。しかし、子供たちの心と体の成長を考えた場合、劇の持つ教育力を、改めて見直す必要があるのではないでしょうか。 「真夜中のサンタクロース」を皮切りに数本の脚本をホームページで発表して以来、秋が深まる頃になると、上演していただいた学校や児童施設、諸団体の皆様からメールや郵便で、感想が届くようになりました。 それらを読むと、天使たちが各地の子供たちに伝えたことは、劇の楽しさだけではなかったことが分かります。 練習が始まった頃は、バラバラだった子供たちの意志や言動が、日を追うごとに、しだいにまとめ上げられていく様子が、何通ものお便りにしたためられていました。 特に、ある児童の感想文にあった「練習中はケンカとかいろいろあったけど、幕が下りるときにみんな涙が出そうになった。」という一文は、私の心を強く打ちました。 努力を重ねることの大切さ、友達とのコミュニケーションや協力することの楽しさ、そして難しさ。様々なトラブルを乗り越えて自分たちの劇をみんなで作り上げた「感動」。天使たちは、これらを子供たちに伝えてきたのでしょう。 劇に取り組む機会に恵まれた子供たちや先生方は、たっぷりと劇の持つ「可能性」を楽しんでほしいと考えます。 また、劇の発表を参観される保護者の皆様は、本番に至るまでの子供たちや先生方の努力に、大きな拍手を送っていただきたいと思います。 |
| 米国と日本の児童劇 私のちょっとした児童劇論 2005.9.30 |
| 今から十年ほど前に、足利市第一次教育訪米団の一員として、姉妹都市のイリノイ州スングフィールド市を視察したことがあります。 このアメリカでの体験が、現在の私の仕事を支えていると言っても過言ではありません。 通訳として経験した英語漬けの日々や、当時の日本では導入前だった教育用コンピュータの学習。そして、現地の「児童劇」との出会いがありました。これは、私にとって少なからずカルチャーショックと言えるものでした。 そのころ、すでに私は児童劇の脚本を何本か発表していましたが、いつも何かが足りないと感じていました。それが何だったのか、この国で、はっきりと発見できたのです。 それは、子供たちが「劇を媒体として観客とのコミュニケーションを楽しめること」さらに、主役の子だけが注目を浴びるのではなく、主役と同じくらいか、それ以上に、「それぞれの役の子供たちが輝けること」でした。 スプリングフィールド市で見た児童劇は、地域の子供たちが取り組んだものです。いわゆるコミュニティー活動と言えるでしょう。演目は、小学校一年生から高校生までの子供たちによる(ちょっと変わった)「ジャックと豆の木」でした。 出演した高校生の話によれば、脚本は出演者全員で意見を出し合って「改良」したそうです。練習では、高校生がリーダーシップを取り、小さい子の役は可愛らしさが出るように、逆に高校生たちは、自分の役を通して、みんなをバックアップできるように心がけたそうです。照明や会場の運営は地域の大人(主に保護者)が担当していました。シアター前では、昔風の衣装を着た中学生たちが、訪れる人々にウエルカムキャンディーを配ったりと、まさに、地域ぐるみの演劇活動でした。 日本の学校で行われてきた学芸会や学習発表会の劇は、教育的な目標がはっきりと打ち出された作品が多く、道徳的で、啓蒙をねらいとしたものが多かったように思います。 劇を通して子供たちに真実を伝えていく教育方法は、決してまちがっていません。しかし、ともすれば、演じる側とそれを観る側とのコミュニケーションについては、希薄になりがちだったようにも思われます。 これからの時代は、子供たちが自由に、思い切り表現方法を工夫できる余地を確保し、仲間や観客とのコミュニケーションを楽しめる脚本が必要だと考えます。 また、私自身、そんな脚本を発表できるように、これからも精進を続けたいと考えます。 |
| 牛乳でカンパイ! 劇の成功を祝って乾杯! 2005.11.18 |
「大成功を祝って、カンパーイ!」 給食当番の声に合わせて、クラスの子供たち全員と牛乳で乾杯をしました。教室には、満足そうな子供たちの笑顔があふれていました。 その日は学芸会。子供たちが発表したのは「バンコートランドの愉快な猫たち〜ヤカンの魔神〜」。当時担任していた4年生の子供たちのために書き下ろした脚本です。 子供たちが持つ無邪気さや好奇心旺盛な姿をモチーフにした猫の国のお話ですが、初演の発表に至るまでには、予想以上に努力や工夫が必要でした。 それだけに、この乾杯は子供たちのみならず、作者である私にとってもうれしいものでした。 現在、インターネットで「学芸会」を検索すると70万件。さらに末尾に小学校を加えて再検索すると23万件のページがヒットします。 多くの学校から消えていった学芸会ですが、しっかりと教育の一部として年間行事に位置づけ、継続している学校があります。最近では、いくつかの小学校のホームページ上で、「猫たち」が活躍している姿も見つかるようになりました。大きな舞台の上で、どの猫たちもみんないい顔をしています。 牛乳で乾杯をした子供たちは、工夫を重ねて練習を続けたり、小道具や大道具を準備する中で、友達と上手にコミュニケーションを取りながら、劇を自分たちのものにしていきました。もちろん、担任には、子供たちの成長を見守り応援する「監督」という大切な仕事があります。 一つの劇を全員で上演するまでの限られた時間。劇に取り組んでいた子供たちは、流行していたインフルエンザの猛威もどこ吹く風。 「先生!このしっぽどうかな?」 「博士ネコはやっぱり白衣を着たほうがいいね!先生、貸して。」 「ヤカンの魔神のターバンは、トイレットペーパーで作れるかも?」 それこそ、登場する猫たちのごとく、楽しそうに試行錯誤を重ねていました。 子供たちの努力と工夫は、学芸会を参観された皆様からの、楽しそうな笑い声と大きな拍手、そして子供たち自身の達成感に変わりました。 「牛乳でカンパーイ!」 給食の牛乳は、紙パックです。 自分たちで「カチーン!」「カチーン!」と言いながらうれしそうに乾杯をしていた子供たち。 感動をありがとう! |
| 1年生、英語劇に挑戦! スプリングビレッジ発英語劇「ふぅあぁゆぅゆぅ?」 2006.1.20 |
| 学芸会を一ヶ月後に控えたある日、一年生の担任の先生方から「英会話学習のようすを劇で表現できないだろうか?」という相談を受けました。 先生方は、英会話学習で見せる子供たちの笑顔や、活気あふれる活動の姿を劇で保護者に伝えたいと考えていたのです。 「英会話学習に児童劇を取り入れることはできないだろうか?」 当時、私も同じようなことを考えいたので、この一年生の挑戦に便乗することにしました。 一年生が演じる英語劇ということで、脚本執筆の際に、三つの柱を考えてみました。 一つは、一年生たちが学習した英会話でストーリーを構成すること。二つめは英語になじみのない参観者でも楽しめる内容であること。そして、三つめは、子供たちや先生方が楽しみながら練習できる劇であることです。 試行錯誤を繰り返し、書き上げた脚本が英語劇「ふぅあぁゆぅ?」です。森にピクニックにでかけた動物たちが、自己紹介や遊びを通してどんどん仲良くなる、というストーリーです。 脚本の完成後、子供たちと先生方は真剣に練習に取り組み始めました。作者の想像を超えるすばらしい工夫や舞台演出がところどころに散りばめられました。 低学年の英会話学習協力員のミラディ先生も、台詞の発音やダンスの振り付けを熱心に教えてくれました。 劇の練習を繰り返すうちに、子供たちは英語の台詞をすっかり覚えてしまったそうです。家庭で両親や祖父母を相手に練習をした、という努力家も現れました。 そして、学芸会当日。 ウサギやパンダ、ライオンやサルたちに扮した一年生たちが次々と体育館のステージに登場しました。ハムスターやイヌ、さらにネコが現れると、動物たちは英語でおしゃべりを始めました。かわいい魔女たちが魔法の杖を振ると、動物たちは英語の歌を歌ったり、音楽に合わせて素敵なダンスを楽しそうに踊り出しました。 この日、一年生の子供たちは見事に、「英語劇」を演じました。 会場からは、子供たちの熱演に大きな拍手が送られました。フィナーレでは、少しばかり照れながらも、満足そうな笑顔を浮かべる子供たちがとても立派に見えました。 新しい年を迎え、三学期となった現在も、一年生の教室から元気な英語の歌が聞こえてきます。英語の劇を演じたことで、また、たくさんの人からほめられたことで、英会話の学習に自信を深めたようです。 子供たちや先生方の新たなる挑戦に期待しています。 今年も、非力ながら応援させていただきます。 *英語劇「ふぅ あぁ ゆぅ?」の詳細はこちらでどうぞ! |
| 卒業生たちよ、幸多かれ! 足利市立梁田小学校の卒業式 2006.3.17 |
いよいよ、卒業シーズンとなりました。 私が現在勤務している足利市立梁田小学校は、本日(3月17日)めでたく卒業式を迎えました。 今年の卒業生は、私が本校に赴任した年の新入生です。丸々6年間の付き合いがあり、担任を持たない立場の私でさえ思い出深い子どもたちでした。 思えば、彼ら(彼女ら)は、情報教育の推進、総合的な学習の正式開始、英会話学習の導入など、教育そのものがめまぐるしく変化した時期の「忙しい子どもたち」でした。 今年、梁田小では卒業証書授与の際に、小学校時代の思い出をステージ上で発表することになりました。子どもたちの心に残っていた思い出とは、いったい何だったのでしょう? 先日行われた予行練習では、宿泊学習、修学旅行や運動会、下級生とのふれあいや教室内外のさまざまな出来事が語られました。 「今年の学芸会で、お客さんが笑ってくれてとてもうれしかったです。」 「大きな声で劇を演じることができてよかったです。」 「練習はたいへんだったけどよい思い出になりました。」 うれしいことに、学芸会の劇の感想を発表してくれた子も数人いました。小学校生活最後の学芸会も、感動の記憶として子どもたちの心の中に残っていたようです。 昨年の冬、6年生は1組が「てんぷく丸東へ!」2組が「鎌倉慕情」を発表しました。 てんぷく丸東へ!は、幕末の動乱を乗り切るために大砲を手に入れようと、米国に渡った武士たちの物語です。鎌倉慕情は、足利市の小学生が修学旅行で訪れる神奈川県鎌倉市を舞台にしたコミカルな児童劇です。どちらの劇も子どもたちのリクエストで取り組むことが決まりました。 練習では、ぎこちなかったせりふや動きが、自分たちで工夫を重ね、先生方からのアドバイスによって生き生きと改善されていきました。 学芸会本番。1組は、手作りの裃を羽織ったサムライたちがりりしい姿を観客に披露し、カラフルな衣装をまとったインディアンたちは楽しい演技を見せてくれました。 また、鎌倉慕情に取り組んだ2組は、悪霊を追い払う女の子のパワーや、そんな女子に圧倒された男の子たちのコミカルな演技が、会場の笑いを誘っていました。 当日、会場の体育館は6年生と観客の熱気に包まれていました。 そして、本日。体育館は、しめやかに卒業式の舞台へとしての装いがすみ、しめやかに卒業式を迎えました。 今、梁田小の校庭では桜のつぼみが弾けんばかりに大きくなり、卒業生たちの門出を誇らしげに見守っています。 子どもたちとのであいに感謝しつつ、卒業生の未来に幸多かれと祈ります。 |
| 教育の原点はへき地にあり 日光市立湯西川小学校へ異動 2006.4.21 |
| この春、縁あって、県南の足利市の小学校から、県北にある新日光市の小学校へ異動しました。ちょうど福島県との県境に位置する勤務校の地域は、気候的に新潟県に近いとされています。 打ち合わせのために三月下旬にこの土地を始めて訪れましたが、道路の両側に押し固められた雪の壁を見てまさに「雪国」を感じてしまいました。 栃木県には、「僻地」と認定されている地域がいくつか存在します。私が新たに勤務する学校もそんな地域の一つにありますが、僻地という言葉から連想されるイメージとは裏腹に、子供たちや先生方はいたって活動的です。 町中の学校に比べ、児童数は少ないのですが、子供たちはとても人なつこく素直です。先生方が子供たちに向ける眼差しにもあたたかさが感じられました。 子供たち一人一人を本当によく理解して絶えず見守っています。 子供たちは「先生方にかわいがってもらっているんだ!」という安心を肌で感じとっているようです。 先日、入学式が行われました。本年度のピカピカの一年生たちは六名です。一年生たちはどの子もニコニコ顔で入場してきました。迎える子供たちも先生方も、心から新しい仲間の入学を喜んでいました。 式後、「今年の新入生歓迎会は、うんと楽しいことをやろうよ!」という声が聞こえてきました。そして、休み時間や学活の時間の教室では、ウキウキしながら自主的に歓迎会の準備に取りかかる子供たちの姿がありました。プログラムを考えている子、花のアーチを作っている子、司会の言葉をメモしている子、そんな子供たちの様子を見ていると、私自身、なぜか、遠い記憶の中にあった「学校」の姿を思い出しました。子供と子供、子供たちと先生方、そして先生方同士の距離がとても近かった時代の懐かしい学校の姿です。 職員会議の中で、教頭先生がこうおっしゃいました。 「教育の原点は僻地にあり。」 とても、意味の深い言葉だと感じています。この言葉の真意を自分なりに解釈できるようになるまで、厳しい冬を何回か経験しなければならないでしょう。しかし、勤務校の子供たちと先生方の関係を見ていると、この言葉の意味が少しだけ理解できたような気がしています。私は、この土地で少しずつ「原点」を極める努力を続けたいと考えます。 しばらく、新日光市の教師としてがんばります。同じ栃木県でありながら、あまり知られていなかった県最北部の教育情報をお伝えできればと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。 |
| 地域ではぐくむ子どもたち 湯西川の大行事「平家大祭のお話」 2006.6.16 |
| 奥日光の山里は遅い春を迎え、目にも鮮やかな新緑が輝きだしました。「平家大祭」と記された赤い提灯が街道に飾られると、日光市湯西川は街中がにわかに活気づきます。 お祭りが近づくと子供たちはウキウキ気分。教室の話題も平家大祭のメインイベント「武者行列」の話で持ちきりとなりました。 武者行列には、小中学校の児童生徒や先生方も参加します。小学一・二年生の児童はかわいい稚児の衣装。三年生から中学生までの子供たちは凛々しい若武者や薙刀(なぎなた)隊、きれいにお化粧を施した白拍子に扮します。先生方は地域の方々といっしょに武将や公家の出で立ちで街道を練り歩くのです。 「エイエイオー。」のかけ声も勇ましく、現代によみがえった平家一族は、日光市長を先頭に、湯殿山神社を出発し、目的地である「復元・平家の里」を目指しました。 この日は晴天。久しぶりに降り注ぐ暑い日差しの中、子供たちは観光客の向けるカメラに思わずポーズをとったり、Vサインを出したりしながら元気に歩き続けました。 少年隊の大将役を勤めた六年生の男の子は、重たい鎧甲を身につけて汗だくになりながらもがんばって歩き通しました。彼は幼い頃から先輩たちが扮してきた大将にあこがれてきたのです。 薙刀隊長を勤める同じく六年生の女の子は、下級生に気を配りながら粛々と目的地を目指しました。彼女も、今年自分が隊を率いることに喜びと責任を感じていたことでしょう。 地域の方々や観光客の声援に応えて、小学一年生から中学三年生までの部隊は、大行列の先陣を切って、全員無事に目的地まで歩き通すことができました。 「来年は中学生だから私は白拍子。」「ぼくは徳子様の旗持ちかも。」行列の終了後、子供たちの思いはすでに来年の配役に飛んでいました。 日光市の北部にある湯西川は、平家落人伝説で全国的に有名な温泉街です。現在、我が国の都市部では、地域の教育力の低下が問題となっていると聞きます。しかし、この小さな街は地域ぐるみで子供たちを育むことを「当たり前のこと」としています。また、小学校と中学校が併設されている学校の中では、小学生、中学生に関わりなく、上級生が下級生を自然にいたわる風潮があり、下級生は上級生にあこがれをいだいているようです。 平成十八年六月六日。 この日、久しぶりに表れた晴天の空は、そんな地域や学校のようすを、伝説の平家武者や姫たちが空の上から見守っていた証(あかし)だったのかもしれません。 |
| 待ちわびていた「再開交流」 再開した湯西川と板橋区の小学生 2006.7.21 |
| 六月三十日。日光市栗山地区の空は、この日を待っていたかのように晴れわたりました。 ドロブックルキャンプ場に到着した二台のバスからは、修学旅行で日光市を訪れていた東京都板橋区の六年生が降りてきました。拍手で一行を迎えたのは栗山地区の六年生十三人です。実に、八ヶ月ぶりの再会でした。 ドロブックルで行われたこの催しは、板橋区立第五小学校(以下、板五小)と、栗山地区にある三つの小学校(湯西川小、栗山小、川俣小)との交流会です。 昨年の秋。栗山地区の子供たちは板五小に、「ホームステイ」でお世話になりました。初めて体験する都会の生活に、最初はかなり戸惑いましたが、板五小の児童や先生方、そして保護者の皆様の温かい心配りにとても感激したそうです。それ以来、手紙を交換したり、ビデオレターを送り合ったりと友情を深め合ってきました。この日は、両方の子供たちが待ちわびていた「再会交流」となりました。 湯西川小の六年生は、出会いのレクリェーションの司会進行を何度も何度も繰り返し練習してきました。努力のかいがあって、本番ではみんなの心を上手にほぐすことができました。 再会交流のメインイベント、ヤマメ・イワナ・マスのつかみどり大会では、キャンプ場に流れる小さな清流に子供たちの歓声が響き渡りました。板五小の子供たちは、はち切れんばかりの笑顔で魚を追いましたがなかなか捕まりません。つかみどりの名人である栗山小の子供たちが、魚の捕まえ方や隠れている場所をていねいに板五小の子供たちに伝授していました。 栗山地区のお母様方に作っていただいた豚汁と、自分たちでとった魚の塩焼き、そしておにぎりをほおばりながら、子供たちはどんどんうち解け合っていきました。 学校のこと、先生のこと、友達のこと、そして今日初めて魚を自分でとったことなど、子供たちの話題はつきることがありませんでした。 やがて板五小の出発の時間が近づいてきました。川俣小の六年生が板五小の児童代表にお別れのプレゼントを渡し、お互いの学校で練習してきた歌を一緒に歌って再会交流は幕を閉じました。 動き出したバスから身を乗り出して手を振る板五小の子供たち。体中でさよならを伝える栗山地区の子供たち。昨年のお別れ会では思わず涙してしまったそうですが、この日はほとんどの子がさわやかな笑顔で手を振り合っていました。 友情が続く限り、友達とは「再会」ができることを、ドロブックルで学んだからでしょう。 |
| 真昼の引っ越し大作戦 学校のお引っ越し 2006.9.1 |
| 湯西川小中学校は、二十五日に一足早く始業式を迎えました。今年の始業式は、新校舎で行われる第一回目の始業式です。 ピカピカの教室、一直線に続く長い廊下、明るくて頑丈そうな階段。ランチルームやホールなど、随所に工夫を施された施設に子どもたち全員の笑顔が輝いていました。 新校舎の完成は、平成十五年の建設委員会発足以来、三年という月日を必要としました。 工事は、湯西川の雪と闘いながら、裏山の掘削、旧施設の解体、校舎の基礎工事、棟上げ、内装工事へと進みました。 「先生、屋根の色が変わったよ!」 「見て!大きな時計がついたよ。」 子どもたちは、旧校舎の窓からそのようすをわくわくしながら見守ってきました。 「新校舎ができるのは楽しみだけど、古い校舎を大切に使おう!」子どもたちは日々の掃除にも力を入れ、思い出深い旧校舎を磨き上げました。旧校舎は新校舎の完成後に解体されることが決まっていました。それだけに一日一日が旧校舎との思い出作りの日々だったのです。 七月下旬。ついに新校舎が完成しました。と、同時に「真夏の引っ越し大作戦」が始まりました。 終業式の日に、小中学生と先生方で第一回目の引っ越しを行いました。この日は、子どもたちが旧校舎に入れる最後の日となりました。小学生は小学生なりに自分たちの持てる荷物を運び、中学生は率先して教材や資料を移動しました。 「いままでありがとうございました。旧校舎での思い出はずっと忘れません。」 作業完了後の、古い校舎の黒板には、子どもたちのお別れの言葉や絵がびっしりと描かれていました。 二回目は夏休み中に先生方とPTAの皆さんとで大きな荷物を移動しました。 重い棚や大型のテレビ、印刷機やコピー機。子どもたちのために、そして学校のために、真摯に荷物を運び上げる姿は、感動的ですらありました。 「先生、中学生のときに、この万力でギターを作ったんですよ・・。」技術室の片隅の錆ついた万力を懐かしそうに見ていたお父さんが教えてくれました。 「私が入学したときは、ここが一年生の教室だったんです。」あるお母さんは、感慨深げに音楽室をのぞいていました。 PTAの皆さんの中には卒業生がたくさんいます。卒業生にとって、この日は旧校舎とのお別れの日でもありました。 子どもたちと先生方、そしてPTAの皆さんの努力によって真夏の引っ越し大作戦は無事に完了。駆け足でやってきた秋とともに湯西川の二学期が始まりました。 |
| 湯西川 教員寮物語 今はなき 大新寮の思い出 2006.9.29 |
| 朝晩すっかり冷え込むようになりました。教員住宅の窓から見える山の木々も秋のフィナーレを飾る紅葉の準備を始めているようです。 湯西川小中学校の場合、私を含め、教員住宅(寮)から学校に通う先生が大部分を占めています。一番大きな寮では八人の先生方が寮長を中心に共同生活をしています。 「ご飯できましたよ〜!」食事当番の先生の声が廊下に響きました。すると、古い建物の中心にある食堂に先生方が次々と集まりました。 今日のメニューは厚切りハムとソーセージミョウガとお豆腐のみそ汁。イカの塩辛と漬け物。そして当番の先生ご自慢のポテトサラダです。 にぎやかな夕食が始まりました。食事中の話題は多岐にわたります。 まず、湯西川の動物たちの近況です。 宿泊学習からの帰り道に車中から五年生たちが子グマを目撃した話。露天風呂で熱心に虫を捕っていたテンの話。車としばらく併走した勇敢な?子ダヌキの話。昨夜聞こえた鳴き声は牝鹿であること・・などなど。 栃木県随一と言われる豪雪地帯で生活するための情報もあります。 毎年恒例となる雪下ろしのテクニック。寮では朝起きると枕元のコップの中身が凍っていること。車が雪に埋もれるとどこに駐車したか分からなくなる話・・新しく赴任した者にとって、とても参考になる話題がたくさんありました。 しかし、やはり先生方です。時折熱心な教育論も展開されます。研究授業のポイントを若い先生に伝授するベテランの先生。学校行事について他の先生から意見を聞く体育主任。明日の授業のネタを仕入れる先生。先生方の話し合いは深夜におよぶこともあります。 そんな話に参加するたびに、この寮生活で培われた先生方の結束力や知恵が長年に渡って学校を支えてきたのではないか?とも考えるようになりました。 すっかり老朽化した教員住宅は、森の中にあります。真っ暗な夜にぽっかりと明かりの灯るその建物から、おいしそうなポテトサラダのにおいが漂ってきました。 「う〜ん、たまらないなぁこのにおい・・。」 木陰に隠れていた子グマが言いました。 「きっとジャガイモで作ったんだよ。」子ダヌキが言いました。 「食べたいなぁ・・ちょっともらってこようか?」テンが身を乗り出しました。そのとき、 「ダメダメ!キューン!」遠くから鹿のお母さんの声がしました。三匹はにおいだけでがまんすることにしました。 そんなうらやましそうな三匹の気配を知ってか知らずか、先生方のお話は続きました。 |
| 鎌倉の大仏様への手紙 合同修学旅行 2006.10.19 |
| 前略、大仏様。 久しぶりに威風堂々とされたお姿を拝見し、とても安心しました。お元気そうでなによりです。 栗山地区の三つの小学校は、栗山連合小学校として修学旅行を行いした。降りしきる雨の中、江ノ電長谷駅で降りた連合小学校の一行は、大仏様のお住まいである高徳院を目指しました。あなたのお姿を発見したとき、子どもたちから大きな歓声があがっていました。 思いもよらぬ悪天候でいくつかの予定を変更しなければなりませんでしたが 「大仏だけは見せたい!」旅行責任者の先生の決断で、久しぶりにお会いすることができたのです。 私は学生の頃からあなたの視線の下で、心の中でお話をすることが好きでした。卒業の年、横浜に残ろうか、それとも栃木に帰ろうかと悩んでいたときに、あなたの螺髪(らはつ)から落ちてきたひとかたまりの雪が、帰郷の決断を促してくれたこともありました。 栃木に帰り教員となってからは、6年生を担任するたびに、高徳院を訪れ、あなたに子どもたちを見ていただきました。それが、いつしか教員生活の喜びとなっていたのです。 「今年の子どもたちはとっても元気がいい。運動が得意になるだろう。」 大仏様がこうおっしゃったその年の6年生は、市の陸上競技会で男女とも総合優勝を果たしました。 「今年の6年生は、みんなかしこそうだ。たくさん本を読ませなさい。」 こうほめていただいたその年の6年生は、3年後の高校入試で全員が志望校に合格しました。 大仏様からいただいた数々の言葉は私の励みとなり、勇気となりました。 「日光から連れてきた今年の6年生はいかがでしょう?」 そう、問いかけあなたを見つめたとき、一しずくの雨が私の目の中に飛び込んできました。その瞬間、あなたの声が聞こえたように感じました。いえ、確かに聞こえました。 「とてもきれいな目をした、素直そうな子どもたちです。その瞳の輝きを失わせないように、しっかり育てなさい。」 大仏様、ありがとうございます。今年の6年生は本当に素直です。素直だからこそ何でも身につけ、真っ直ぐに伸びていくことができるでしょう。私はそんな素敵な子どもたちをこれからも応援したいと考えています。 大仏様、どうぞ鎌倉の空の下から子どもたちをお守りください。 追伸。だいぶ寒くなりました。風邪など召さぬようご自愛ください。 それでは、またあえる日まで。 草々 |